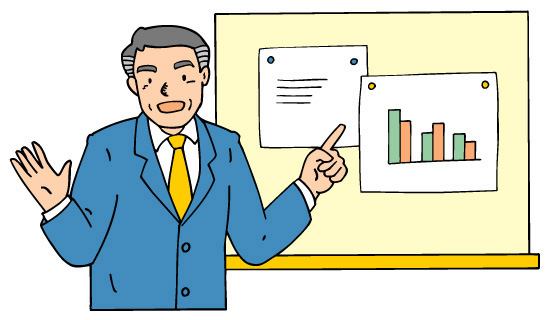特許権を有する者は、特許をライセンスするにあたり契約書を作成することが通常です。
以下では、特許ライセンス契約書の見るべき重要なポイント、すなわち、特許ライセンス契約の勘所について、ライセンサー側の立場、ライセンシー側の立場を踏まえて概観したいと思います。
なお、ここでは、特許ライセンス契約書の規定されている条文の順番に捉われず重要な点の説明に絞っておりますので、特許ライセンス契約に関する具体的なご相談をご希望の企業様につきましてはお問い合わせフォームより弊所弁護士へご連絡をお願い致します。
特許ライセンスの目的と事前検討
特許ライセンスの目的は、ライセンサーの立場としては、特許の有効活用、具体的にはライセンス料収入を得ること、ライセンシーの立場としては、開発費用削減、開発失敗リスク回避、さらには特許侵害回避、特許紛争の早期解決等があります。また、近年はオープンイノベーションも盛んであり、自社にない技術について外部から導入するという目的で、特許ライセンス契約の重要性が注目されており、これに対応する弁護士や弁理士も存在しております。
友好的な特許ライセンスと敵対的な特許ライセンスとでは、ライセンス交渉の状況は異なりますが、いずれにせよライセンシーとなろうとする者は、自社製品、若しくは今後販売予定の製品がライセンス対象特許の技術的範囲、すなわち、権利の範囲に含まれているのかを検討する必要があります。
なお、特許の技術的範囲の判定は、技術的かつ専門的ですので、この点は特許を扱う弁護士や弁理士へ事前に相談されたほうがよい点となります。また、権利の有効性、権利の存続期間等、ライセンスを受けようとする権利の状況については原簿等で確認必要となります。
特許ライセンス契約書の勘所

当事者について
ライセンサーとなる者は、通常、特許権者ですが、特許権者から専用実施権を付与されている者や特許権者から再実施権許諾された者もライセンサーとなることがあります。なお、特許が共有の場合には、共有権利者の一人である特許権者も単独でライセンサーになることは可能ですが、共有者の同意がなければ、第三者にライセンスすることはできません。この場合、ライセンサーに同意が得られている点について表明保証してもらうか、同意書の提示を受けることなどが必要となります。
ライセンシーは、ライセンス対象特許の実施を求める者です。もっとも、契約主体自体は一社かもしれませんが、ライセンスを受ける主体の範囲に親会社や子会社等も含める場合もあります。ライセンスを受ける主体の範囲については、親会社のような密接な関係を有する会社であっても契約書に明記しておかないと、後で揉めることにもなりますので注意が必要です。
対象特許について
対象特許の特定
基本的には、現存する特許権が対象となりますが、特許出願中のもの(特許を受ける権利)であってもよく、また、外国における特許もライセンス対象とすることは可能です。特許は出願日から20年で権利が消滅し、特許維持年金支払未納等によっても消滅しますので、特許ライセンス契約締結時点において、対象となる特許の有効性、存続期間満了までの年数等は、ライセンシーの立場では確認する必要があります。この対象特許の調査については、特許に携わる弁理士や弁護士が常日頃からアクセスしている特許庁のプラットホームにおいて簡易に確認でき、さらに、特許原簿等を取り寄せ確認することができます。
なお、ライセンス対象特許について契約書の中では少なくとも特許番号で特定し、外国特許の場合は外国特許番号や国名、出願中の権利であれば出願番号等で特定することが通常行われています。出願番号、出願日、発明の名称等も記載されていることもあります。複数特許ライセンスや包括的なライセンス契約の場合、契約書本文ではなく別紙でライセンス対象特許を特定することも行われており、契約後にライセンス対象特許が追加されるような契約や出願中の権利も含むような契約となっている場合、別紙を差し替えてライセンス対象の特許を追加・削除、番号変更していくことも行われています。
対象特許の特許維持、訂正承諾
特許ライセンス契約では、ライセンサーにおいて特許維持年金を支払う等、ライセンス対象特許を維持すべき最大限の努力を払うという特許維持義務が規定されることが多いです。
また、この特許維持義務に合わせて、ライセンシーの訂正承諾義務が規定されることがあります。訂正承諾義務とは、ライセンサーが対象特許の権利範囲について訂正審判や訂正請求を行う際、ライセンシーの承諾が必要となるため、これを予めライセンス契約書においてライセンシーの承諾を取り付けておくということが行われています。訂正承諾義務については、ライセンサーとしては忘れないようにしたいところです。
対象特許の保証等
ライセンサーは、ライセンス対象特許の実施において、他社の権利を侵害しないという点については通常保証しません。他方、ライセンシーに対しては、市場でライセンス対象特許の侵害行為が行われていることを発見したような場合に報告義務等が規定されていることが多いかと思います。この報告を受けたライセンサーが、さらに侵害除去する義務を負う形とするのか、義務を負わないのかという点については、ライセンサーとライセンシーの力関係で決まるところになります。
改良発明
ライセンシーがライセンス対象特許に関連する発明をした場合の取扱規定が契約書中に導入されているケースが多く見られます。ライセンサーは、ライセンス対象特許に派生する権利であることを理由に自社にも実施できるようにしたいと考えますし、他方でライセンシーは、自ら発明したものでありライセンサーが発明に関与していない以上、何らの権利も与える必要がないと考え、この点については対立することがあります。
特許ライセンス契約における改良発明の取扱いについては独禁法ガイドラインに記載もあり、同ガイドラインを踏まえ検討する必要があります。一つの落としどころとしては、ライセンシーがライセンサーに対して改良発明について実施権を与え、その対価を有償とするというのが本来的には公平ではないかと思いますが、この点については色々な形があります。
不争条項
不争条項とは、ライセンシーが、ライセンス対象特許について特許無効審判等を起こすことで対象特許を消滅させる行為を禁止するというものです。ライセンサーは、ライセンシーに対してライセンス供与する代わりに特許の権利の有効性について争う余地をなくすというものであり、特許ライセンス契約書の多くにこの条項は規定されています。ライセンサーとしては、対象特許の不争条項が入っていることは必須です。また、ライセンシーがダミー(ライセンシーが準備したライセンシー側の者)で無効審判等を提起してくることを回避するため、ライセンシーが間接的にも特許の有効性を争えないようにしておく必要があります。また、この条項にライセンシーが違反した場合には、ライセンサーとしては即刻契約解除ができると規定しておくべきです。
特許ライセンスの形態について

基本枠組
特許ライセンスについては、独占的な契約とするのか非独占な契約とするのかという点は、契約上大きな枠組みの一つです。
独占的な特許実施許諾には、専用実施権設定のような形、すなわち、ライセンサー側も実施できず、ライセンシーだけが独占的に実施でき、第三者にも実施許諾しないという形、もしくは、ライセンシーに実施の許諾を与えた上、ライセンサーは原則実施できるがライセンシー以外の第三者に権利を付与しないという独占的実施権の形が考えられます。他方、非独占的な実施許諾とは、ライセンサーがライセンシーの実施を容認するだけであり、ライセンサーは自社実施可能で、また、第三者にも実施許諾することができる態様をいいます。
ライセンサーである特許権者の立場としては、自ら実施する場合には、ライセンサーが実施可能な形で独占権を付与する独占的通常実施権、また、非独占の実施権とすることが一般的には望ましいことなります。他方で、ライセンシーとしては、ライセンス料との兼ね合いもありますが、可能であれば独占的な実施権を希望することも多いでしょう。もっとも、事業との関係でどのような形にすべきかは個々の案件で異なることになります。
当初は独占的なライセンスとしておいて、一定条件を満たさないようになった場合に非独占へと転換する転換条項を設けることもあります。ライセンサー、ライセンシーの事業における位置づけ等を踏まえ、弁護士等の専門家を交えるなどして枠組みを決定します。なお、独占的ライセンス契約を締結する場合、ライセンシーとしては先行する実施権者が存在すれば対抗されてしまうことになるため、先行ライセンシー不存在についてライセンサーに表明保証させることも行われています。
実施の範囲
ライセンスの実施の範囲について通常ライセンス契約書で規定されることになります。特許法では実施行為が定義されておりますので、特定の行為(製造・販売のみ等)だけに限るのか、全部の行為を認めるのかを具体的にライセンス契約書に記載しておきます。また、特定の型番の製品の製造・販売だけに限ったり、製造可能な数量を制限したりすることもあります。また、実施し得る場所的な範囲について、我が国とするのか、外国のどの国を含めるのかについても検討が必要です。
これら実施の範囲については、ライセンス契約書で明確に定義しておかなければ、後日争いとなることがありますので、ライセンサー、ライセンシーとも共通認識となるよう定義規定を設ける等して、後日その文言解釈において疑義が生じないようにしておく必要があります。勿論、ライセンス期間については、ライセンシーにとって重要なことですので、この点もしっかり合意することが必要となります(ライセンス期間については後述。)
サブライセンス
ライセンシーが直接、特許製品を製造・販売するようなケースであれば、再実施権(サブライセンス権)は不要となりますが、グループ企業に実施させるようなケースは勿論、他の第三者に実施させるケース、一部を委託するようなケース、将来的に自己実施せず第三者に実施させることを考えているなどの場合、再実施権付きのライセンス契約を結ぶことが必要となります。ライセンシーとしては将来の自由度を確保したいため再実施権付きが望ましいのは当然ですが、ライセンサーとしては、サブライセンスの付与は可能限り避けたいというのが実情かと思います。ライセンサーとして再実施権許諾をする場合には、無限定となると将来の自社事業に影響を及ぼす可能性がありますので、許可条件(具体的な会社名、グループ会社に限る、都度ライセンサーの事前承諾等)を付与しておく必要があります。
なお、ライセンシーが特定の会社に製造下請等させる場合、サブライセンス権の付与を受けなくても可能な場合がありますが、ライセンサーの許諾不要な下請けの要件は判例上明らかにされているものの、事実認定の問題もあり、確定的に判断しきれないため、ライセンシーが下請に委託することを考えている場合、当該下請先についてサブライセンス権を付与してもらうか、下請けを行うことについて契約上、明確にしておいたほうが安全です。他方で、ライセンサーとしては、下請を一切禁止する、また特定の下請け先に限るということも契約上明記することも一考です。
特許ライセンス料(実施料)について
ライセンス料(実施料)及び計算方法
ライセンス料をいくらとするかは、当事者間の合意により定まるものであり決まったものはありません。ライセンス契約締結時点で、最初に一時金(イニシャルロイヤリティー)の授受をした上で、以後、ランニングロイヤリティーを支払うケースや、単にランニングロイヤリティーだけを支払うケースが一般的です。
イニシャルロイヤリティーが支払われる場合には、独占的実施権を付与するようなケースで採用されることが多いと言えます。
ランニングロイヤリティーには、販売単価に販売数量をかけた売上額に対して、さらに料率をかけて計算した金額が採用されることが多いですが、売上額にかかわらず、一年間でいくらという形の定額で支払われるケースもあります。料率については何%とするのかはライセンサーとライセンシーの間の合意で決まるものですから決まった数字はありません。また、販売単価についても、卸単価を用いるケースもあれば、小売単価を用いるケースもありますし、販売数量については生産数量で計算することもあります。
ミニマムロイヤリティ―、すなわち、特許製品の売上額にかかわらず、年間に最低支払わなければならない金額が別途規定されることもあります。これも独占的実施権を付与するケースで多く見られるものです。独占的実施権を付与すると、ライセンサーは第三者に特許をライセンスして収益を上げることができない、また、自社実施も不可という状況であれば、さらに特許を利用できないという不利益があるため、独占的実施権の場合にはライセンシーに最低金額を保証させるという趣旨があります。
ライセンサーとしては、独占的実施権付与の場合、一般的にはイニシャルロイヤリティーやミニマムギャランティーを含むランニングロイヤリティーの対価支払いとなるよう進め、ランニングロイヤリティーについても可能な限り高額となるよう交渉を進めていくのが通常です。他方、ライセンシーとしては、全く逆の動きとなります。ライセンス交渉段階で、弁護士が関与することもありますが、弁護士が介入することで紛争が顕在化することを避ける意味で弁護士なしで交渉されるケースも多く見られます。その場合には、弁護士は交渉の相談だけを行い、その後、双方で合意ができた段階で、特許ライセンス契約書の作成やレビューを担当することもあります。なお、ライセンス料の支払時期については、年1回とする場合もあれば、四半期毎や毎月とする場合もあります。このあたりは、特許製品の特質等を踏まえ合意により決まるものとなります。
報告、帳簿閲覧権
ライセンス料支払いの報告について、通常は、ライセンス対象となっている特許製品の販売数(生産数)、販売単価、売上額等を報告する義務がライセンシーに課されることになりますが、具体的な販売先についても報告の対象となることがあります。いかなる点を報告の対象とするのかについては、しっかりライセンス契約書で明記する必要があります。また、報告義務についてどの程度の頻度で報告するのか(通常はライセンス料の支払い時期とリンクさせていることが多い。)についても検討が必要です。
もっとも、ライセンス料の支払いにおいて毎回個別にその報告する数字を裏付ける資料の提示を求めることは稀であり、通常は、お互いの信頼の上、ライセンシーによる自己申告という形になります。ただ、ライセンサーが、市場に出回っている数量等からみてライセンシーの報告した数量に疑義が生じるような場合もありますので、ライセンサーとしてはライセンシーの報告内容を確認するための術を準備する必要があります。
特許ライセンス契約においては、ライセンサーは、ライセンシーの会社内に立ち入り検査できるようにしたり、ライセンシーの持つ帳簿を閲覧できるような規定を設けることが多いかと思います。ライセンシーとしては、このような規定が導入された場合、これを断る理由はなかなか見出しにくいところがあります。もっとも、自社のライバル会社であるライセンサーに対して、会社の財務状況、特許製品に関する情報を直接開示するのはあまり好ましくないという考えがありますので、中立の第三者である公認会計士に限って閲覧等が可能とするとの文言を追加することで対応することもあります。
ライセンス料の返還
ライセンス対象特許が、ライセンス契約締結後に特許無効となった場合や、出願中の対象特許が最終的に拒絶となった場合、ライセンス契約においてどのように取り扱っていくのかについて、契約書中で合意するのが通常です。一般的には、特許無効や権利拒絶が確定した段階までに支払われたライセンス料については返還しないとすることがほとんどかと思います。ライセンサーとしては、ライセンス料の不返還規定については必須となります。
特許ライセンス期間の終了時期について
特許ライセンス契約は、当事者間の合意である以上、特許ライセンス契約が継続する限りにおいて双方に何らかの権利義務が生じるものであり、当事者としては、この状態から脱してライセンス契約を終了させたいということがあります。ライセンス契約における終了規定としては、契約期間満了、中途解約、約定解除等があります。

契約期間満了
契約期間満了は、当初合意していた契約期間を満了すれば、ライセンス契約が終了となることを意味しますが、自動更新の規定があればそれに従うことになり、特許ライセンス契約では最長ライセンス対象特許の存続期間満了まで自動延長されることが多いかと思います。
ライセンシーとしては、一般的には契約期間自体を可能な限り長くし、自動延長等を設けず、最初から契約期間を特許の存続期間満了までとしたいところです。途中でライセンス切れとなると、そこで事業が頓挫し、そこまで積み上げた設備投資も無駄となってしまうリスクを避けるためです。もっとも、独占的ライセンス等でミニマムロイヤリティーを支払っているような場合、ミニマムロイヤリティ(実施料)の支払いが負担となる場合もあるため、この点については長ければ長いほうがいいとまでは言い切れません。
他方、ライセンサーとしては、非独占のライセンス契約であれば、いつでも自社実施でき、また第三者にライセンスを付与することは可能ですので、ライセンシーの意向どおり存続期間満了までであっても特段大きな問題は発生し難いと思われます。もっとも、独占的なライセンスの場合には、自社実施が妨げられ、また第三者にもライセンスできず、ライセンシー以外からの特許による収益を上げることができなくなります。そのためライセンサーとしては下記の約定解除において一定要件下で契約解除できる条項を設けたり、一定条件下で独占的なライセンス契約から非独占的なライセンス契約への転換条項を設けておく必要があります。
中途解約
中途解約については、ライセンサーが一方的に無理由で解約できる条項を入れると、ライセンシーの事業が立ち行かなくなる可能性があるため、ライセンサー側からの中途解約についてライセンシーが了解することは通常ありません。そのため、この規定が導入されるとすれば、ライセンシー側にのみ認められる一方的条項となると考えられます。もっとも、ライセンシーにだけ認めるのは公平の観点から、ライセンサーがこの要求を受け入れることは少なく、結局のところ、ライセンス契約において無理由の中途解約条項が入るのはあまりないと思われます。
約定解除
約定解除については特許ライセンス契約においては重要となります。
ライセンサーとしては、ライセンシーのライセンス料の不払い等の債務不履行は勿論、ライセンシー側の信頼破壊行為(ライセンス対象特許に対する無効審判提起等)等があれば、契約を継続することはライセンサーにとってマイナスでしかありませんので、契約を解除できる条件を特許ライセンス契約書中で具体的に明示しておくことが重要です。
他方、ライセンシーとしては、中途解約を求めるケースとしては、ミニマムロイヤリティ支払いを逃れるため等が考えられますが、これを解除理由とするわけにはいかず、結局のところライセンシーが約定解除する場合というのは、ライセンサーによる債務不履行や信頼関係破壊行為等があった場合に限られるということになります。
その他
表明保証
前述のように特許が共有の場合、ライセンシーがライセンスを受けるためには共有特許権者の同意が必要となり、ライセンシーとしては、ライセンス対象特許が共有の場合に他の権利者の同意を得ていることをライセンサーに表明保証してもらうことがあります。また、前述のとおり独占的ライセンスの場合に先行ライセンシーが存在が疑われるような場合、そのようなライセンシーが存在しないことをライセンサーに表明保証してもらうこともあります。その他契約中で表明保証させたい事項を弁護士等の専門家に具体的に話をして、契約書中に落とし込む必要があります。
技術援助
ときどきライセンサーからライセンス対象特許のライセンスを受けただけでは、ライセンシーがその対象特許を使いこなせない場合があり、ライセンサーが、ライセンシーに対して、特許ライセンスすることとは別に、具体的な技術導入について援助したりアドバイスしたりするケースがあります。このような場合には、特許ライセンス契約の中では詳細を定めず、別途技術援助契約等が締結され、そこで細かい合意がなされることが通常です。
一般条項
秘密保持、権利義務の譲渡、裁判管轄等、特許ライセンス契約には、通常の契約と同様に一般条項も規定されていますので、この点の細かい確認も必要となります。
特許ライセンス契約の総括
以上は特許ライセンス契約書において、特に重要な部分を抜き出し、チェックすべき勘所をご説明したものですが、ここですべてではありません。
特許ライセンス契約書は、昨今ではネット上に雛形も存在しますが、記載されている内容が複雑であり、ライセンサーとなるのかライセンシーとなるのかで修正すべきポイントは大きく異なるため、特許ライセンス等、特許に関する契約実務に精通している弁護士へご相談されるのがよいと思います。
また、特許ライセンス契約締結の前提として、本当に契約を締結すべきものなのかの検討、すなわち、貴社の製品がライセンスを求める特許の技術的範囲に含まれているかについても、弁護士や弁理士の専門家の視点での検討が必要です。
お問い合わせ方法
弊所では、特許ライセンスの相談、特許ライセンス契約書作成やレビュー等について、弁護士弁理士が対応しておりますので、ご希望の企業様は、お問い合わせフォームより弁護士へお問い合わせください。