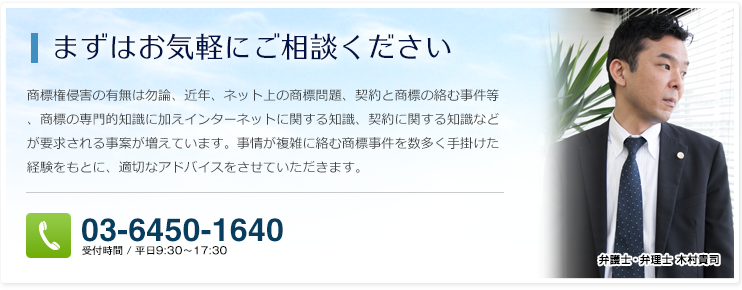商標の類否の判断基準
商標の類否の問題は、審査時において、類似する先行登録商標があった場合や商標権侵害の際、登録商標とイ号商標が類似するか否かという判断をする場合にでてくる問題です。
商標権侵害か否かについては、商標が同一又は類似、商品役務が同一又は類似のいずれかに該当する場合です。商標が類似するか否かは、原則として、商標が有する「外観」「称呼」「観念」という要素を比較検討し、さらに取引の実情を考慮した上で、これらを総合して商標が似ているか否かを判断します。「外観」は商標の見た目であり、「称呼」は商標の読み方、「観念」は、商標から生じるイメージです。この点に関しては有名な氷山印事件という最高裁判例(昭43・2・27)があり、そこでは、
| 「商標の類否は,対比される両商標が同一または類似の商品に使用された場合に,商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによつて決すべきであるが,それには,そのような商品に使用された商標がその外観,観念,称呼等によつて取引者に与える印象,記憶,連想等を総合して全体的に考察すべく,しかもその商品の取引の実情を明らかにしうるかぎり,その具体的な取引状況に基づいて判断するのを相当とする。」 |
とされています。すなわち、商標の類否というものは出所混同のおそれがあるか否かで決するとされているところ、外観、称呼、観念を対比し全体観察によって、しかも具体的な取引の状況を考慮して総合的に判断するとされました。また、外観・称呼・観念のうち一つが類似する場合であっても、他の二点が著しく相違する場合や出所混同を生じるおそれがないような場合には類似しないとされます。
結合商標の類否判断
商標権侵害訴訟における商標の類否で問題となる多くのものは、いわゆる結合商標に関するものです。審査段階における結合商標の類否判断について、最高裁(H20.9.8)が下記の規範を示しました。その後、侵害訴訟においても同様の基準が使われています。
| 「複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについて,商標の構成部分の一部を抽出し,この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは,その部分が取引者,需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や,それ以外の部分から出所識別標識としての称呼,観念が生じないと認められる場合などを除き,許されないというべきである」 |
さらに最近の知財高裁(H27.11.5 侵害事件控訴)では、上記とは別の従前の結合商標の判断に関する最高裁判例(S38.12.5)の内容と組み合わせて下記のような基準を定立しています。
| 「複数の構成部分を組み合わせた結合商標については,商標の各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認められる場合において,その構成部分の一部を抽出し,この部分のみを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは,原則として許されない。他方,商標の構成部分の一部が取引者,需要者に対して商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や,それ以外の部分から出所識別標識としての称呼,観念が生じないと認められる場合などには,商標の構成部分の一部のみを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することも,許されるものということができる」 |
結合商標の場合には、全体観察することが原則とした上で、分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているとまではいえないような場合には分離観察が許容され、一つの構成部分が取引者,需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められるか、他の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められる部分を認定した上で、再度全体又は分離観察によって類否の判断をしてもよいと述べらている、と私は考えています。そして、これらを判断するために、商標の構成、使用態様、取引実情等を緻密に事実認定されることとなります。商標権侵害訴訟の裁判においても、いかなる事実が認定できるのか、また、それをどのように評価するのかという点が争いになり、商標権侵害訴訟における弁護士による主張立証活動の大きなところとなります。結合商標は実務上頻出問題ですので、裁判例を見ながら実務感覚を養っておく必要があります。
なお、上記の知財高裁の定立した基準について、特許庁は私の考え方とは異なる考えを取っています。すなわち、分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているとまではいえないような場合には、当然に分離観察が許容される。他方で、分離観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合している場合でも、「一つの構成部分が取引者,需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められるか、他の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められる場合」には分離観察が可能であると考えているようです。
特許庁の考え方は分離観察を基本的に認めるという、これまでの実務との整合を図ったもののようですが、私自身は、現段階では上記のとおり、不可分的に結合している場合は当然に全体観察(分離観察は不可)、不可分的とまで言えない場合にはじめて分離観察は許容され、その上で最高裁(H20.9.8)の基準で判断するという立場です。
お問い合わせ
商標権侵害の成否を決定づける商標の類否の問題、その他商標に関するご相談につきましては、「お問い合わせフォーム」から、又は下記お電話までお問い合わせください。